粉瘤
【粉瘤、読み方:ふんりゅう、別名:アテローム(atheroma)、表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)】
皮膚の下に袋状の構造物ができたものです。
内部には、本来は剥がれ落ちていくはずの垢(アカ)や、脂腺からでた脂が詰まっています。
中央に開口部がある方とない方がいます。
周囲から押すと、臭くてドロっとした粥状の物質が開口部より出てくることがあり、患者さんによっては「脂肪がでてきた」と言われる方が多いですが、実際は脂肪ではなくて主に垢です。

粉瘤の大きさ、部位、感染・炎症をおこしているかどうか(膿んでいるかどうか)によって、対応方法が変わります。
患者さんの粉瘤の状態に応じて、一番よいと思われる手術方法を提案いたします。
粉瘤の切除の方法は?
炎症を起こしていない粉瘤の切除方法は「紡錘形切除」と「くり抜き法」のどちらかが行われます。
当院では病変部の状態に合わせて「紡錘形切除」と「くり抜き法」のどちらが最適かを判断して施行いたします。
① 紡錘形切除(スタンダードな切除法)
最も一般的な術式です。
当院では炎症がなければ「紡錘形切除」を第一選択の術式としています。
状態・大きさ・部位などを考え「② くり抜き法」を行うこともあります。不明な点があれば、医師にご確認ください。
嚢腫の大きさ・部位に合わせて紡錘形(木の葉の形)に切開いたします。
粉瘤の壁を見つけて、壁に沿って袋状の嚢腫を丁寧に摘出します。
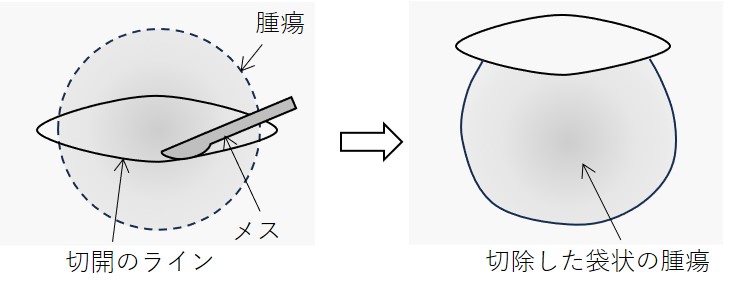
欠損部を縫合して創を閉じます。
通常の大きさであれば、内部を縫合して、表面を縫合して2層で縫います。
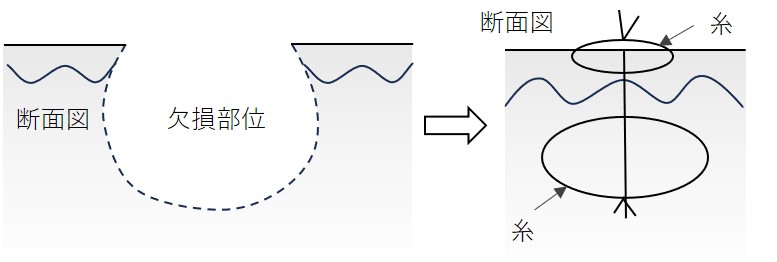
表面からみると、縫合部は以下のようになります。
表面の糸は1~2週間を目安に抜糸いたします。
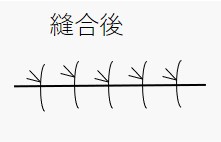
② くり抜き法(臍抜き法)
腫瘍部位に小さな穴をあけて、内容物(貯留していたアカ・皮脂)を出します。
その後に小さな穴から腫瘍の壁を摘出します。
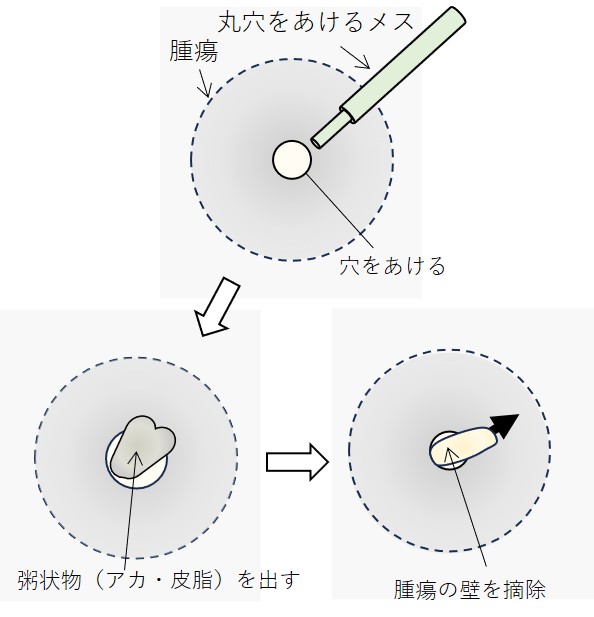
腫瘍の壁をできるだけ、丁寧に剥離して摘出します。
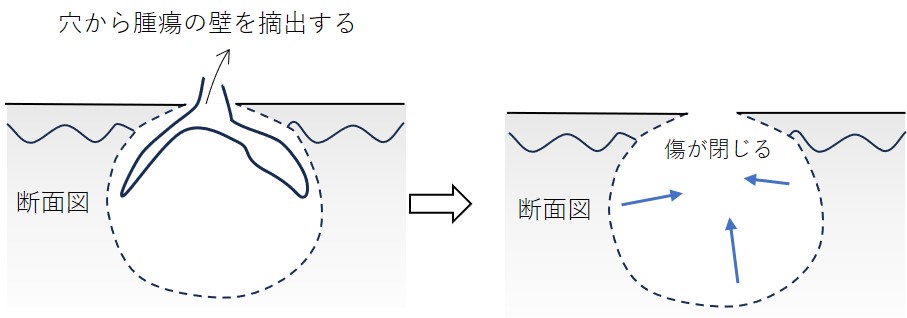
摘出後は、自然に創部が閉じるまで待つか、縫合します。
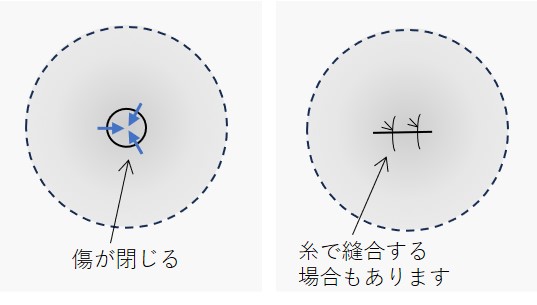
※壁が全摘できないことがあります。そのため、紡錘形切除(①)に比べて再発率が高い(10~15%程度)(文献参考値)です。
全身麻酔で切除した方がよいくらい大きい場合などでは、病院(基幹病院・大学病院)をご紹介することもあります。
切除までの流れ
切除をご検討の方は、注意事項を以下のページで説明していますのでご参照ください。
粉瘤が腫れています!その時は?
粉瘤はときどき、炎症や感染を起こします。
そのようなときは対応法が変わってきます。
切開して排膿処置を行ったり、抗生剤で経過をみたりします。その後、炎症を抑えてから後日に根治切除を行うことが一般的です。
状態によりますが、ときには当日くり抜き法に準じた治療を行うこともあります。
Q&A
Q どうして粉瘤はできるのですか?
ㅤ


